
相続について
身内がいて、その方が亡くなれば相続は必ずご自身に降りかかってくる問題です。相続の基礎知識についてご説明します。

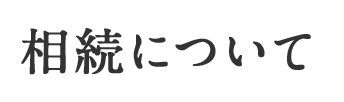

故人の財産が現金で遺されていて相続人が複数いる場合、その現金の配分は遺言書に記された比率、遺言書がない場合は法律で定められた配分比率に則って、相続人同士の話し合いによって決められることが多くあります。
故人の財産が金融機関に預けられていた場合、金融機関はその預貯金の名義人の死亡を確認した時点で口座を凍結してしまいます。
したがって、その後は払い戻し請求を受け付けません。払い戻しをするためには、口座の名義変更が必要となります。
故人の口座が凍結された後の名義変更手続きと払い戻し請求には、次のようなケースがあります。
名義変更手続きは、ケースによって若干必要な書類が変わります。場合によっては書類の種類が増え、印鑑もいろいろ必要になってくるため、とても面倒な手続きとなります。
お電話いただければ手続きについてアドバイスをさせていただきますので、電話無料相談をご利用下さい。
専門家の司法書士にお任せいただければ、速やかな処理が可能です。
お話をお聞きいただいたうえで当事務所でも手続き業務を承る事は可能です。

相続財産の中に不動産がある場合、自宅や農地、収益を得るアパートなどそれぞれのケースで相続手続きもいろいろです。ここでは、よくある自宅を相続する場合についてご説明します。
不動産を相続する場合、代表的な方法として次の3つがあります。
不動産は、遺言書または遺産分割協議書で示されていない限り、すべて法定相続分に準じて相続が行われ、全相続人の共有となります。しかし、できれば相続人の中の誰か一人が名義を取得するような形式をとるほうがよいでしょう。
というのも、同じ不動産を複数の人が共有していると、その方たちが亡くなった場合、共有関係がより複雑になってくるからです。また、共有者全員の承諾がなければ、その不動産に手を加えたり売却することもできません。それが後々の争議の種になりかねませんので、当事務所では代償分割、または換価分割をお勧めしています。

財産を相続した人は、その財産の内容を申告し、相当額に応じた納税を行う義務があります。申告・納税の期限は、相続人となったことを知った日の翌日から10カ月以内で、申告・納税の場所は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署です。
相続税は、相続した財産すべてに課税されるわけではなく、基礎控除額というものが設定されています。
基礎控除額は、次の計算式に基づいて決められます。
5,000万円+(1,000万円×相続人の数)=基礎控除額
つまり、課税されるのは、相続財産がこの計算による金額を超えた分だけということです。実際、この控除額はかなり大きな金額です。ですから、よほどの資産家でもない限り、普通は相続税の心配をする必要はあまりないといえるでしょう。
但し、27年1月からはこの基礎控除額が以下の通りに変更されます。
3,000万円+(600万円×相続人の数)=基礎控除
となります。相続税を納めなければならない例が急増しそうです。そのために、生命保険、遺言書などを活用した相続対策が必要になります